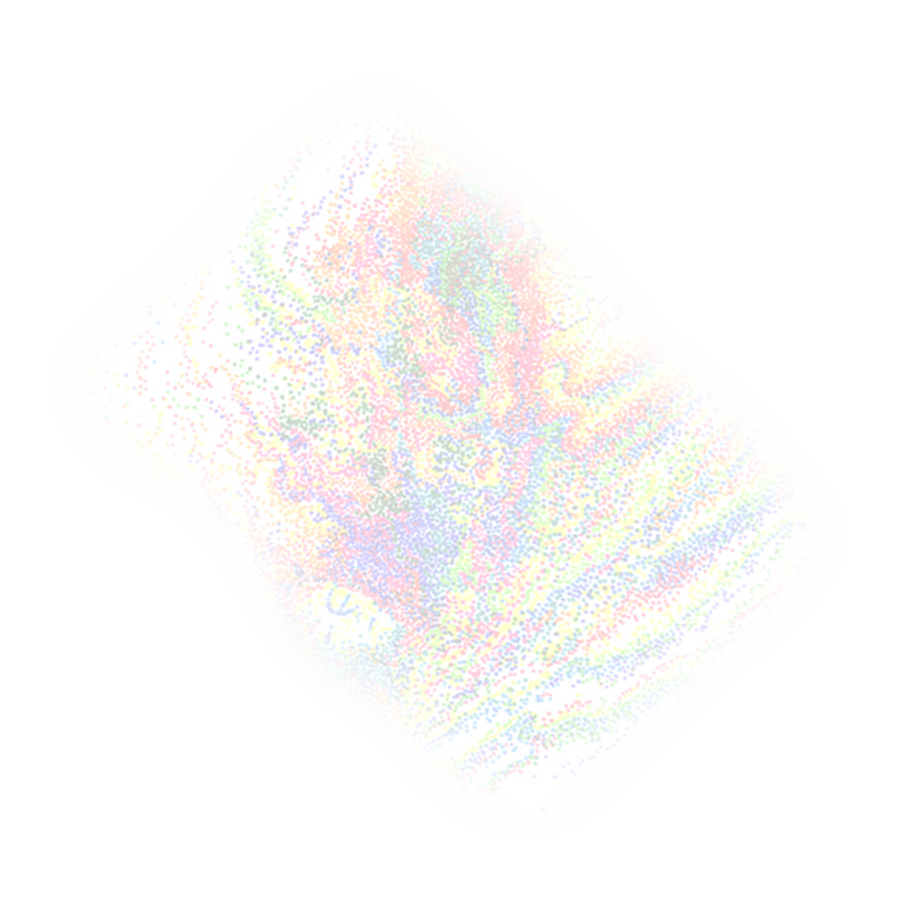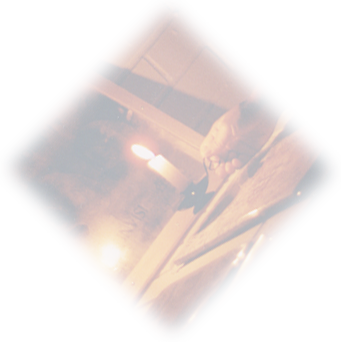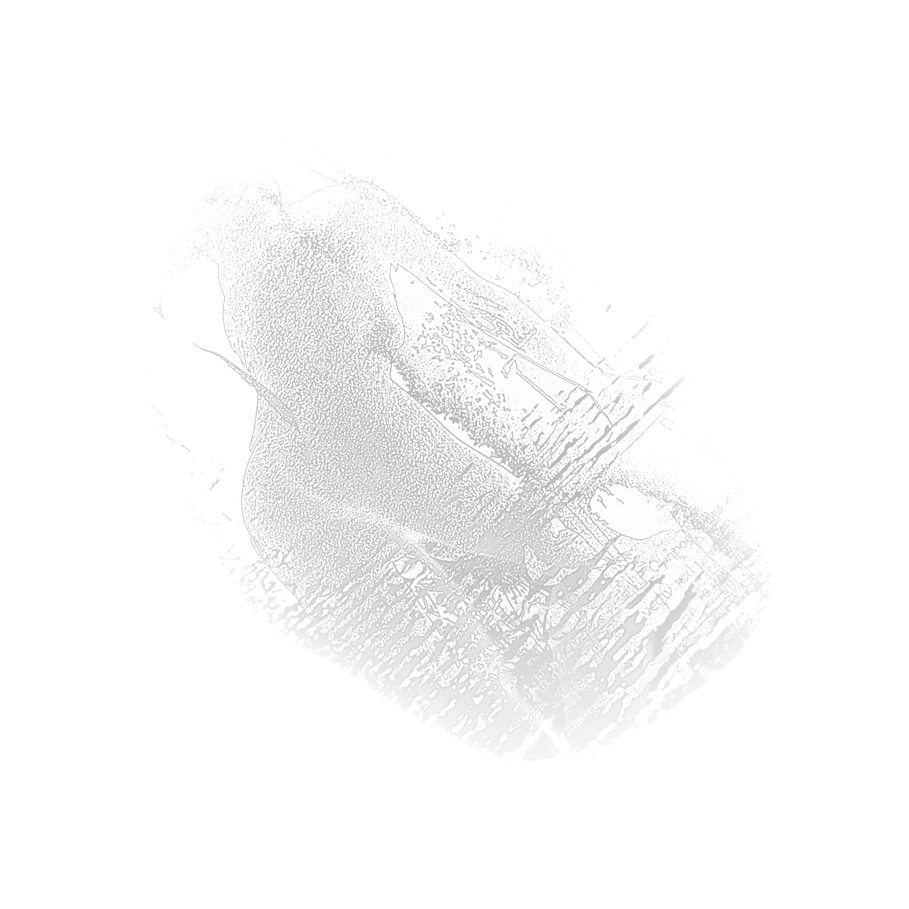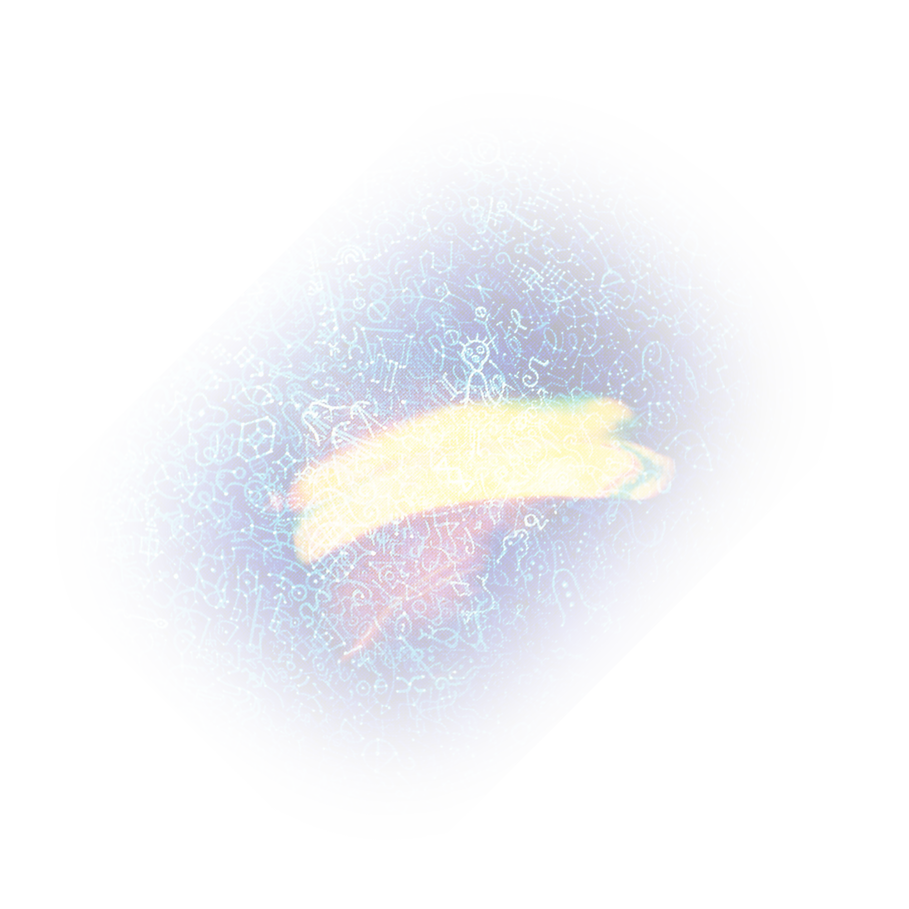01 はじめに・輝く光
光について、なにかを書こうとすればするほど、書くことがなにもないのに気づく。
光は単に光であって、その中には内容というものがなにもない。だから、本質的に、光については、書くことがなにもない。光の本質は、無である。
逆に、闇というものは、きわめて内容が豊かで、その中にはなんでもある。いろいろなものがありすぎて、かさなりまくって、なにがなんだかわけがわからなくなって、結局すべては闇の中に溶けこんでいってしまう。
巷間、いわゆる「精神世界」系の本などを読むと、光というのは、けっこう評価が高い。『光の世界』への憧れとか、『自らの中の光に気づきましょう』なんてことが、山のように書いてあります。
私は、こういう感じの光への評価に接するたびに、???と思ってしまう。
これは、別に私がひねくれものだから……ということではなく、実際、単なる光というのはつまらんもんです。
光への憧れというのは、結局、自分の脳の中を空っぽにして、気分良くたゆたいたい……という身勝手にして幼い?欲望のような気がする。自分がとにかく気持ち良くなりたい……という、いわば赤ちゃんレベルの話ではないだろうか。
逆に、闇というと、普通、ものすごく嫌われる。埴谷雄高さんが大好きというような人は別として、とくに最近は、はやりません。
世界史を動かす闇の力……なんでしょうか。だけど、もしそういうものがあるとして、そういうことにたずさわっている方々は、自分や自分がやっていることを、闇だと思っているのだろうか?
アレキサンダーは、ゴルディアスの結び目*1をばっさりやっちゃったといいますが、闇をばっさり解決するのは、結局は「力」なのでしょうか?
個人の心の闇……私にとっては大事なものだけれど、他の人にとっては存在してもらいたくないものなのかもしれません。「オタク」という言葉のどこか湿っぽく暗い響き……「光オタク」……精神世界マニアの人はこんな感じですが、これは、結局言語矛盾なんでしょうか?
自分自身、これまで作品を作ってきたり、いろいろ考えたりしてきた経過をたどってみますと……やっぱり、あるときは「光オタク」であり、はたまた「闇オタク」であったような気がします。
02 見せない試み
私は、最初の個展*2に、INVISI(アンヴィジ)という、何語かわからないようなタイトルをつけました。
日本語訳もありまして(これも勝手な訳ですが)「否視」(ひし)といいます。つまり、見ることの否定です。
私は、それまで、アクリル絵具で神社なんかを題材とした、けっこう神々しい?絵を描いていました。→リンク
こういう絵の評価はまっぷたつで……そういうもんが好きな人は「すばらしい!」なんていうけれど、精神世界的な「単なる光」を嫌いまくる人もいて、そういう人には「ああ、そっち系の絵だね」という扱いでした。
それで、私自身、それまでの自分の作品のつくり方に一旦訣別しよう……という意図も湧いてきて、『否視』なんてコンセプトの個展をやろうと考えたのです。
会場には、今まで描いてきた「神々しい」作品を展示する。だけどその作品を見ることはできない……という状態をつくる。
具体的には、まず、作品をそのまま壁に掛けるのですが、その上を、透明ビニールにいろいろな図柄をプリントしたもので覆ってしまいます。作品より一回り大きな木枠を作り、その木枠に図柄をプリントしたビニールを張って、作品は、そのビニールの図柄を通してやっと見えるか見えないか……という構成。
さらに、会場全体を真っ暗にして、手に持つロウソクの光で見てもらおう……という趣向です。
会期中、二人、ユニークな人がいました。
お一人は、現代美術家のMさん。
Mさんは、ロウソクを拒否して真っ暗な部屋の中に入り、十分くらい出てきませんでした。遮光はかなり念入りにやったので、中は、相当暗かったはずです。一体、どうなっていたのでしょう?
もう一人は、Nさんというもの書きの方です。
この方が会場に入っていかれてしばらくすると、なにかガタガタと大きな音がしました。それで、会場に入ってみますと、なんと、手前の木枠に張ったビニールの邪魔者を外して、壁に掛かった作品を見ようとされていました。
ある意味、このお二人の行動は、まったく対照的でした。このお二人以外の方は、みなさん、おとなしくロウソクをかざして見ておられました。
03 脳の中の光は、どこからくるのか?
この個展をやってみて、あとから思ったことですが、この個展の会場構成は、なんとなく、われわれの脳の内部を思わせるのでは……ということです。
脳の中は、ほぼ真っ暗なはず。しかし、私は「光」を感じる。
外からの光は、網膜で止まる。そこから先は「電気信号」の世界。それは、おそらく最後まで「電気信号」の世界なのでしょう。「化学反応」も入るのかもしれないが……しかし、脳内で「光」は復元されない。
では、私が感じているこの「光」は、いったいなにものか??
頭を開いて、脳に直接光を当てる。しかし、目を閉じていれば、光は感じられない?
私は、常に、「翻訳された光」を見ているということになるのでしょうか?
では、「光」とはなにか。
物理的定義はあるのでしょう。
しかし、私が、今、感じている「この光」は、なんだろうか?
「この光」は、私の脳の構造とおそらく密接に絡んでいて、それゆえに、「私の精神」にも、「私の心」にも、深く関係したものでしょう。
少し前、ジェームズ・タレルさんの回顧展*3で、チラシに「夢の中の光はどこからくるのか」と書いてありました。
では、そもそも、脳の中の光は、どこからくるのでしょう?
04 拒否する光
光は光でも、すべてを拒否する鉄壁の光。
昔、セシュエーという方の書かれた『分裂病少女の手記』という本を読んだことがあります。
セシュエーさんは精神科のお医者さん(女性)で、彼女の患者さんで、ルネという女性の手記をまとめたもの。
ルネは、子供のころから精神分裂病(今は統合失調という?)になり、のちに奇跡的に回復するのですが……回復後、自分が分裂病に苦しんでいたときのことを手記にまとめた。
その中では、光は、「拒否するもの」として登場します。
すべてが光に照らされた世界。
それは、人の参加を拒否し、圧倒的な支配力で、人の自我を押し潰しにかかってくる。光の、すべてを拒否する力の前に、人の自我は、無力にも、その統合を喪失していかざるをえない。
そこでは、どんな抗弁も無駄。全部光の壁にはねかえされる*4。
まるで、ナチスの裁判のようなもの……でしょうか(体験したことないですが)。
この本は、かなり昔に読んだのですが、その当時は、不謹慎ながら、「面白そうな体験もあるものだ」という理解でした。ただ、光というものが、すべてを拒否するものとして扱われているところが新鮮で、そこは鮮明に記憶に残っていました。
普通は、「やさしく包み」、「受けいれ」、「高めてくれる」ものとしての光が、ここでは全く逆で、「冷たく拒否し」、「あくまでよそよそしく」、「自我を崩壊させる」ものとして登場するのです。精神世界系の人の語る光の作用と、まったく逆になっています。
ところが、最近ある方から、光についてのやはり似たような体験を聴くことができ、人が自我、すなわち個というものをきちんと保つためには、やはりある程度の闇は必要なのではないか……ということを考えるきっかけになったのです。
05 個と全体
われわれは、なぜ、個であるのか? 私にとっては、このことは、幼いころからの根本的な疑問でした。
昔、子供のころ、実にバカな?疑問を抱きました。
それは、「私は、なぜ、王選手ではないのだろう?」というものでした。
別に、王選手が好きでも嫌いでもないのですが、なぜか突然、こんな疑問が浮かんできて、これについて、自分なりにいろいろと答を考えたことを思い出します。
なぜ、私は王選手でなくて、私なのか?
別に、私が王選手であって、王選手が私であってもちっともかまわないではないか?
なのになぜ、私は私の中にいて、王選手は王選手の中に(多分)いるのだろうか?*5
小学生くらいの子供は、よく、自分のお父さん(あるいはお母さん)は、実は自分の本当の親ではない、自分の実の父(母)は、別にいるのだ!と、なんの根拠もなく思ったりするとききます。
私も、実は、小学校3年くらいのとき、学校で、植物学者の牧野富太郎博士の写真の入った「しおり」を貰ったのですが、そのしおりを見ているうちに、「そうか!自分の本当の父親は、この牧野富太郎博士だったのだ!」という強烈な確信がむりむりと湧きあがってきたのを思い出します。
しかし、この、「なぜ、自分は王選手ではないのか?」という疑問は、それよりもう少し根源的なものだったように思います。
そして、あとになってわかってきたことは、この疑問は、正しくは(というと変ですが)「なぜ、自分は自分なのか?」というさらに普遍的な疑問に統合されるということです。
つまり、「個」としての問題、インディヴィデュアルの問題です。
06 クィディタス ハエッケイタス
以前、N大のO教授のスコラ哲学の講義を聴いたことがあります。
スコラ哲学というと、とにかく理屈っぽくて、議論の堂々めぐりというイメージが強いものですが、この講義で、私が一番びっくりしたのは、「天使の中で、一番頭の悪いヤツと、人間の中で、一番頭がいいヤツとでは、どっちが頭がいいのか?」というようなテーマが、現代でも大論争になっているのだ……という話です。さすが、スコラ哲学。映画『コンスタンチン』*6の世界が、そのまま出現したような迫力。
こういう、奇妙な?スコラ哲学の世界で、『クィディタス』と『ハエッケイタス』という、不思議な一対の言葉に出会いました。
哲学辞典を見ますと、『クィディタスQuidditas』*7は『通性原理』、『ハエッケイタスHaecceitas』*8は『個性原理』と訳されていて、これらの言葉は、結局、存在の普遍的な側面と個的な側面にかかわるもののようです。
『クィディタス』は、ラテン語のQuid(疑問代名詞の中性単数形。what)から、『ハエッケイタス』は同じくラテン語のHaec(指示代名詞の女性単数形。this)から、おそらくきているのだろうと思いますが……ここで、突然、話は、フランク・ハーバートさんの長編SF『デューン/砂の惑星』*9に飛んでしまいます。(跳躍だらけですみませんが)
この小説は、デビット・リンチ監督がロマンティックな映画*10にもしていますが…原作は一種のサガで、何代にもわたって続く物語です。
舞台は、砂の惑星アラキス。超巨大生物であるサンド・ワーム(メーカー、創造主とも呼ばれる)が造りだすスパイス、メランジをめぐって、銀河系のさまざまな勢力の争いが繰り広げられる…という設定ですが、ここで、主人公のポウル・アトレイデという少年が、成長して、「クイサッツ・ハデラッハKwisats Haderach」という存在になる…ということが書かれています。
「クイサッツ・ハデラッハ」なんて、音感的にはアラビア語風ですが、物語の風情も多分にアラビア的で、聖戦ジハードなんてのが出てきたりします。9.11のテロ以降、イスラム世界が話題になりますが、この物語は、それより40年近く昔に、イスラムの世界観にアプローチしようとした試みでもありました。
「クイサッツ・ハデラッハ」というのは、単に「救世主」ともいわれていますが、私の理解の範囲内では、「普遍的存在であると同時に個的存在でもある」存在(のあり方)ということだったと思います*11。
とすると、これは、どうしても、スコラ哲学の『クィディタス』と『ハエッケイタス』を思い出さざるをえない。この物語の作者のフランク・ハーバートさんは、スコラ哲学の勉強もされたのでしょうか?
スコラ哲学は、古代ギリシアが滅びたあと、アラビアに受け継がれた古代ギリシア哲学が発展したアラビア哲学の影響が色濃いといいますから、そのあたりの関連もあるのかも知れません。
07 暗い家にすむ子供
ということで、個と全体の探求ということになってしまいました。というか、「全体」というわからないものはまず置いといて、個が個である、さらにいうなら、私が私であるというのは、結局どういうことなのか? 私が私であるには、何が必要なんだろう……?ということです。そして、結局、私は、「個」というものを成立させるには、どうしても、定かならぬ淵に溶け込んでゆく闇の深みが必要…ということを言いたいのだと思います。
では、個が闇なら、全体が光なのか…といいますと、そうでもないのですが、この、全体の話は先にいったようにしばらく置いといて、もう少し、個と闇について、考えてみたいと思います。
易に、「山水蒙」(さんすいもう)という卦があるそうです。易は、ご存知のように、陰と陽の組み合わせで六四通りの卦*12をつくり、それによってさまざまな事象を占うものですが、この六四通りの卦の中に、「山水蒙」と呼ばれる卦があります。
「蒙(もう)」は、「暗い」という意味だそうで、だから「蒙を啓く」ということで「啓蒙」になるわけですが…その感じからもわかるように、「蒙」という文字は、単に明るさ的に「暗い」ということだけではなく、「開かれていない状態」のようなものを現しているようです。
昔、黄小蛾という方の『易入門』*13という本を読みましたが、この本では、この「山水蒙」の卦のことを、「暗い家に住むこども」と表現してありました。
この表現は、まさに「蒙」という文字のキャラクターをぴったり表すもので、私は、大いに感動?した覚えがありますが…これは、今でいうと、まさに「オタク」そのものですね。
闇を内に抱えて、眼は、その「内なる闇」に向いています。人は、個を個として意識しはじめたときから、「個」は果てしない深みに続く闇の淵となり、その強い「引く力」は、人の存在の在りようを、有無をいわさず規定してしまいます。
昔は、こんなのを避けようとするために?(かどうかは知りませんが)、丁稚奉公という立派な制度がありました。
とにかく、青少年は、自分という「暗い家」の中には置かない。その力に捉えられる前に*14、ぴかぴかと明るい「昼の光」の中に引きずり出して、立派な?社会構成員となれるように厳しく鍛えあげる…ということで、丁稚奉公システムによって「個」というものを一切否定しつくされた青少年は、「社会」の鋳型に叩き込まれて、立派なオトナになっていったのでした。
これは、日本だけじゃなく、外国でも…かもしれません。かのレオナルド・ダ・ヴィンチだって、ヴェロッキオの工房に入らなければ、かなりの「オタク」になって大成は望めなかった??
ということで、「個としての闇?そんなのは置いといて、立派なオトナになるのだ!」というシステムが全般的に機能していた時代は、おそらく「オタク」は少数の者にだけ許される非生産的快楽だったのでしょう。しかし、今は…逆に、殆どの青少年が、この「個としての闇」にはまらざるを得ない状況になってしまっていると思いますね。
08 カラマゾフの兄弟
ドストエフスキーの『カラマゾフの兄弟』の中に出てくるエピソード。
ある人が、「人類救済」の理念に燃えます。自分の心の中で、全人類に対する愛が、いやがうえにも燃え上がってきて、もうそのためには、自分はなんでもしたい……なんでもできる!と思う。
だけど、この人は、実際に肉体を備えた他人が傍らに出現すると、もうダメです。他人のちょっとした癖が気になって、二日と同じ部屋にいられない。相手がどんなに立派な人でも、その人を憎み嫌うようになるのにそんなに時間はかからない。
で、彼は、この矛盾に悩むという次第*15。
このお話を読んで、私は、「個としての闇」というものの根深さといいますか、ちょっとどうしようもないような「途方にくれた感じ」がよくわかりました。
全人類に対する愛…というのは、それは、この上はなにもないくらい立派な、ぴかぴかの光なんでしょうが……でも、その中には、なんにもないのです*16。
逆に、「個としての闇」を覗くと、そこには、わけのわからないものがやたらに重なりまくっていて、結局、なにがなんだかわからないうちに、なにもできずにただただ途方にくれるだけ……になってしまいます。
全人類に対する愛…では、やっぱり、光りすぎてだめであると。
で、「国」とか「故郷」とか「地域」とか「会社」とか「家族」とかは、光としては、ちょうどいいのかもしれません。
人は、それぞれ、キャパに応じていろんな共同体を「光」とすればいい。
丁稚奉公システムは、「家族」ではないが、しかし程よい大きさの、いわば社会的なレベルの最小限の「光」からはじめるためには、本当にいい訓練システムだったのでしょう。
でも、青少年にモラトリアムができると、彼の妄想は、「自分」から、一気に「全人類」に飛んでしまいます。
「自分」という、底知れぬ闇の淵と、「全人類」という、膨大ではあるが内容のまったくない光…。
これは、やっぱり、だれが見ても極端ですね。
09 蛍の光
3年半前に、街から田舎に引っ越しました。
愛知県の「奥三河」と一般的に呼ばれる地域の、入口にあたるところなのですが、典型的な山里で、目の前に田んぼが広がり、小高い丘があり、落葉樹の林があり、小川になだらかな山……そして、水は山の湧き水という生活。
ここで、はじめてホタルを見ました。
というか、見たのは、蛍の光。
初夏、暗くなってうちに戻る。車のライトを消して田んぼの方を見やると、ふっとかきけすような光の弓。
しばらくするとまた。目がなれてくると、けっこういくつも見えます。
その光は……想像していたものとはかなりちがって、まさに「いのち」そのもの。
考えてみれば…光って、太陽や月や星の光を別にすれば、今まで「人工の光」ばかり見てきたんですね。
「いのちの光」がこんなふうに見えるものだとは……ちょっと感動でした。
それで思い出したのが、やっぱり、ジェームズ・タレルさんの作品。
彼の作品の光は、なぜか、このホタルの光によく似ている。
人工光源の光を使うこともあれば、自然光を使うこともある彼の作品ですが……、たとえ、人工光源の光でも、彼の作品の光には、「いのち」を感じる。
光が……光の粒子の一粒一粒がいのちをもっていて、空間に染みだして、見るものに語りかけてくるような……。
なぜ、そんなことができるのでしょう?……不思議です。
10 なにも運ばない光
考えてみれば、すべてのアート作品は、光というものぬきには考えられない。
なぜなら、まったく光がないと、全部闇で、なにもわからないから。
しかし、かならず、光は、なにものかを運ぶ媒体として使われている。
形であったり、色であったり、明暗であったり、意味であったり……。
つねに、従としての、めだってはならない立場ですね。
ところが!
タレルさんの作品では、この、光そのものが、作品そのものでした。
なにも運ばない、それ自身としての光……。
こういう光を見たのは、ほんとうにはじめての体験……。
目が、開かれる思い。
考えて見ますと……セザンヌ以降の現代美術の流れというものは、絵画から、いかに意味を抜いていくか…ということの歴史であったような気がします。
つまり、物理的にそこにある絵画というものは、昔は、それによって「運ばれる意味」というものが必ずあったのだが……現代美術は「意味を運ぶ船」であることを拒否し、船自体の存在を世に問うた。
しかし、まだ、実は奴隷がいたのです。
それは、光。
だれもが、光をなんらかの媒体として用い、しかも、そのことをほとんど意識しなかった。
タレルさんの作品は、そこに切りこんでしまった……というわけですね。
11 美と崇高
光そのものとは、なにか。
カントは、『判断力批判』の中で、「美」と「崇高」の問題を扱っています。
詳しい内容は忘れましたが、「崇高」という言葉は、聳え立つ高山や、広大な海原、嵐……といった自然現象に関係して用いられていたように記憶します。人間ワザをかけはなれた事象……ということでしょうか*17。
とすると、ジェームズ・タレルさんは、アーティストの中で、はじめて?「美」ではなく、「崇高」の領域を目指したお方……ということがいえるのかもしれません。
少なくとも、彼の作品制作動機は、すでに「美」ではなく「崇高」への志向性ではなかったかと感じます。
継続中の、ローデンクレーター・プロジェクト*18なんかには、とくにそんなものを感じますね。
そして、「崇高」の感情は、「美」よりもさらに宗教的感情に近いように感じます。
天空や、海や、山や、大地、そして深い森や巨石や洞窟に、「神」を見る心……
タレルさんは、「神が殺された」現代…のアーティストですが、なぜか、古代の人々の「神」を見る心と近いものを感じるのは、私だけでしょうか?
そして……究極の「崇高」は、やっぱり「光」そのものなんでしょう。
12 むすび・輝く闇
なぜ、タレルさんの作品が、光でありながら、単なる光であることを免れているのか。
それは、彼の作品の光には、そのものとしての命(いのち)がある……からだと思います。
そして、それはまた、彼の作品の光が、今までのなにかを運ぶ奴隷という立場から開放されて、「光そのもの」として立ち現れていることと無関係ではないでしょう。
蛍の光……は、蛍にとっては自己そのものである……がゆえに、その光は、蛍そのものの命(いのち)となります。
同じように、タレルさんの作品の光は、自己そのものであるがゆえに、それは、命(いのち)となることができるのであると思います。
とすると、われわれの個としての闇も、また、自己そのものとして立ち現れるとき、それは、闇でありながら、光となることができるのかもしれない……。
私自身は、自分の作品の中で、ずっと、そのことを追い求めてきたように思います。
輝く闇……
蛍が、無限の闇の中で、自己そのものとして一瞬、輝く弓となるように……
しかし、また再び濃い闇があたりを包み、歴史は閉じられる。
輝く闇は、あくまでも闇であり、光にならない。
だから、たとえわずかであっても、「内容」というものを、自らのうちに持つことができるのであると思います。
そして、ここに立つとき……私は、はじめて「本当の世界」が私の前に広がっているのを見る……ことになるのでしょう。