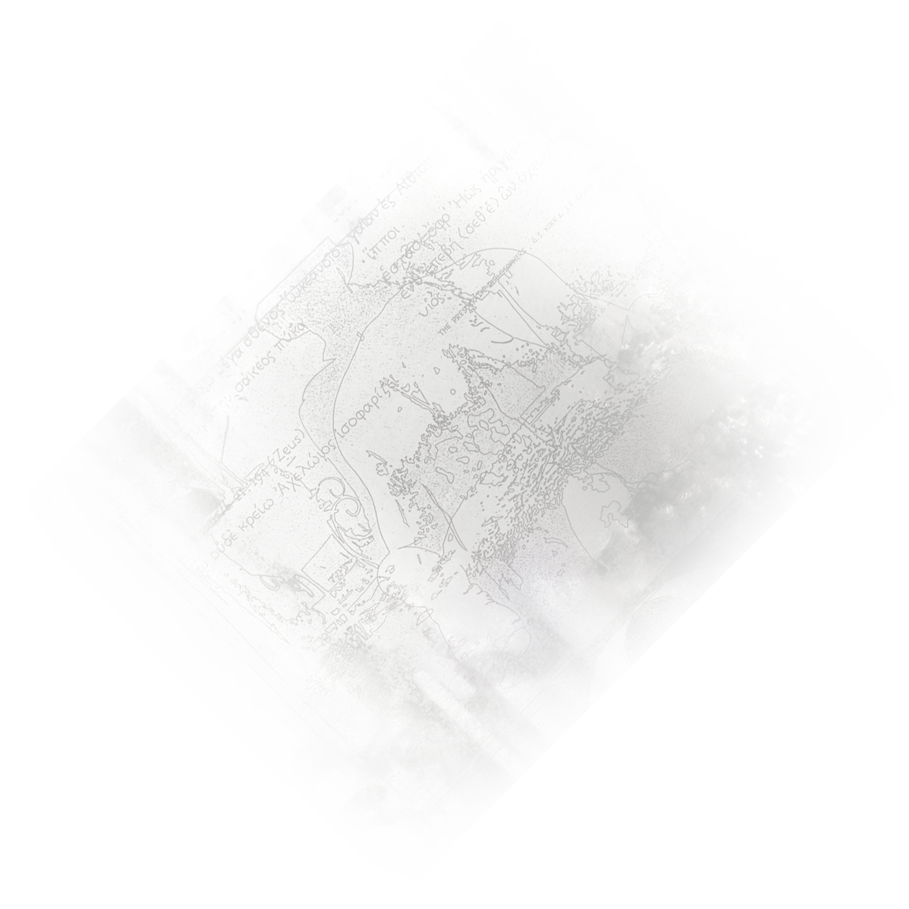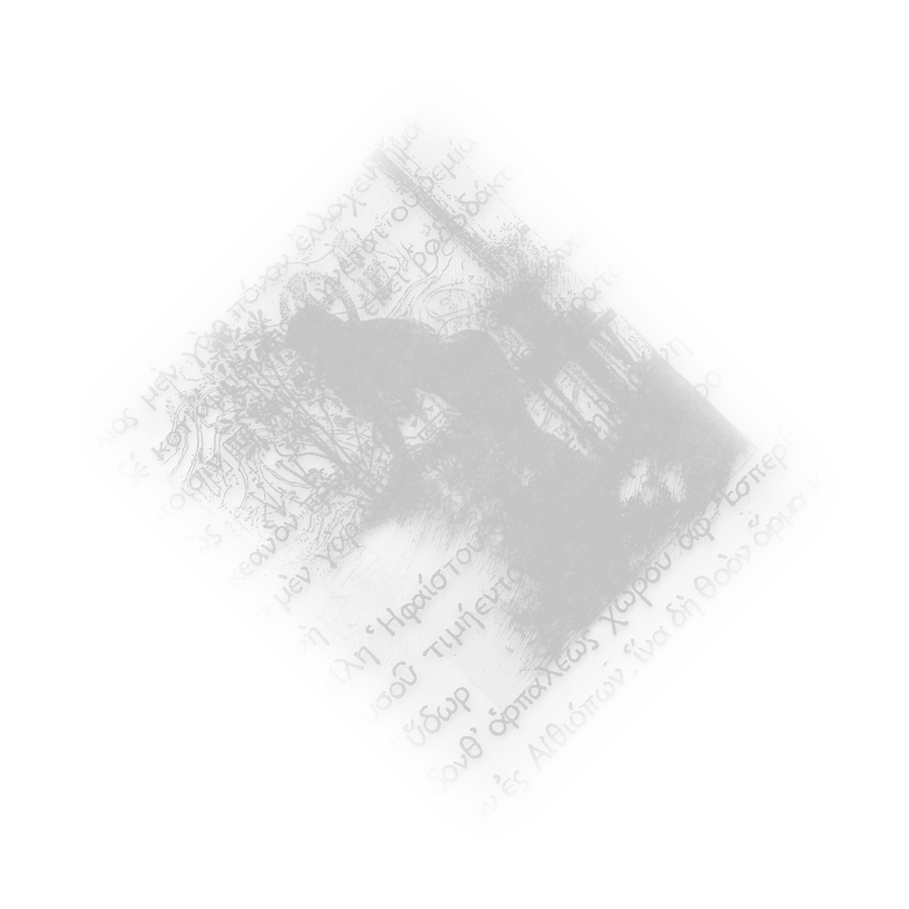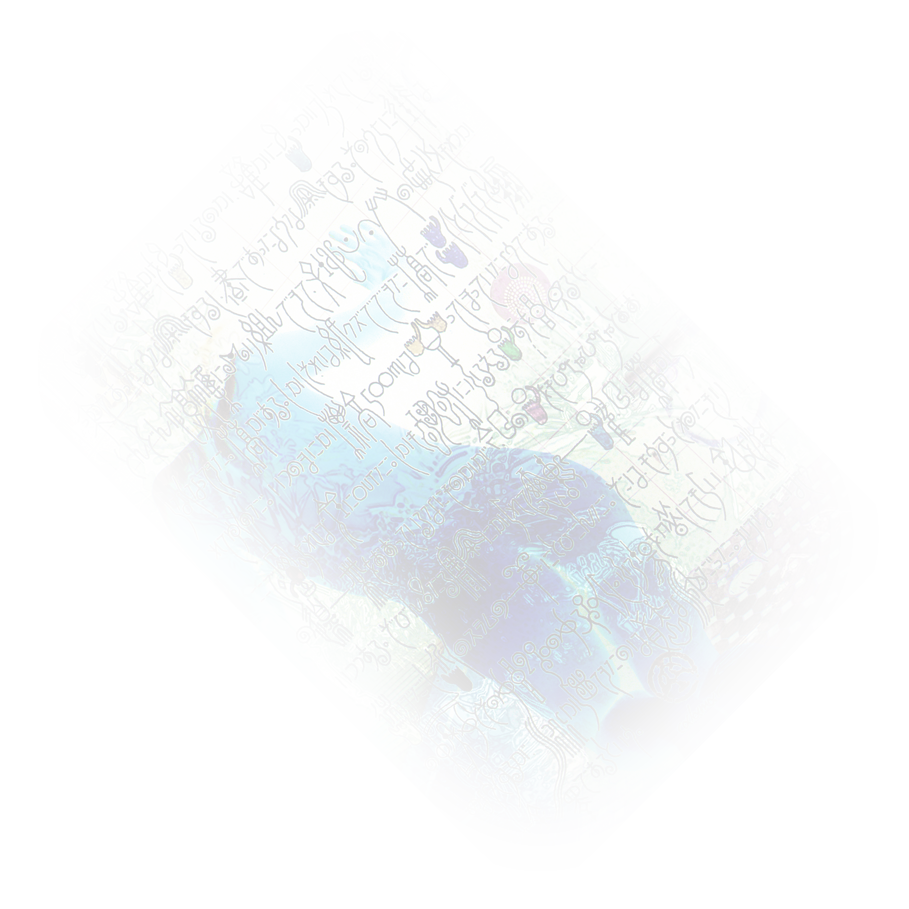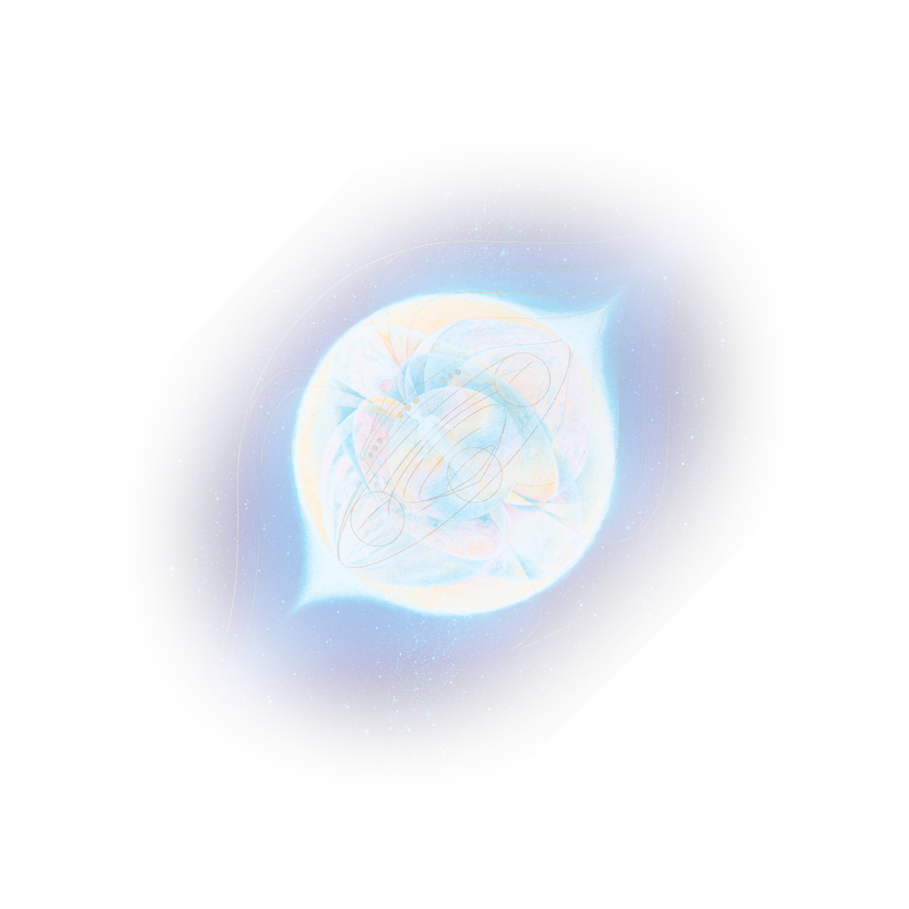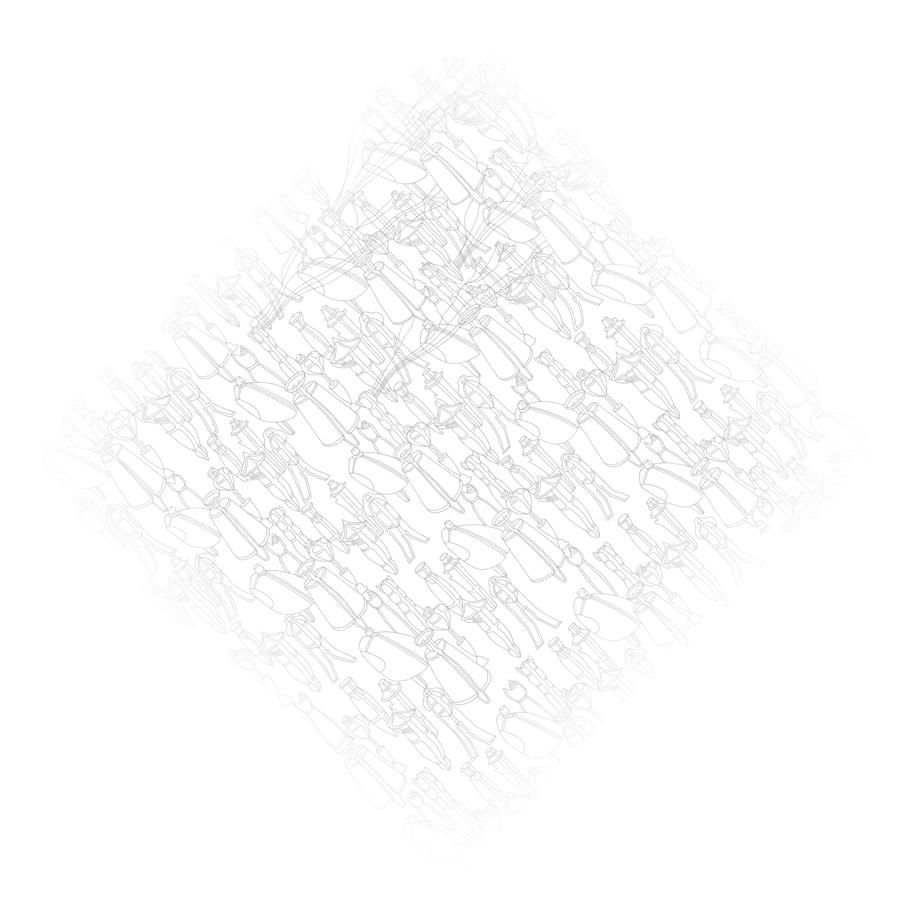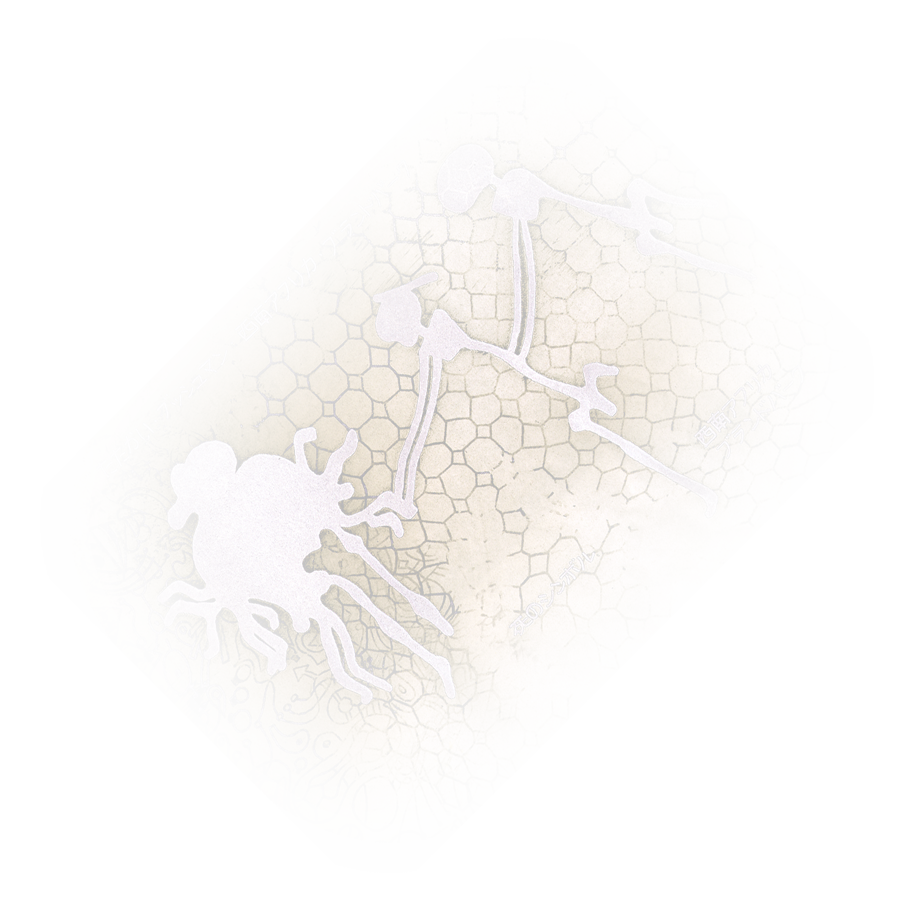1.恐怖の写本人間
とにかく「写す」ということが好きです。
新聞にチラシ広告が入っていると、それを写す。新聞そのものも写す。
本を写す。絵も写真も写す。景色も建物も、いろんな雑貨も、とにかく写す。
「写す」ということは、私にとって「世界の確認」なのでしょうか。
「写す」働きは、いわゆる「ドローイング」になるのでしょうが、それは行為の結果にアート技法を貼りつけるときにそうなるのであって、やっぱり基本は「写す」でしょう。
「写本」CODEXという言葉は、やっぱり基本的には「テキストを写す」つまりは文字を写すということになるでしょう。(ちなみに、CODEXという言葉はもともとラテン語で、木の幹や本、会計帳簿などを意味したが、英語では写本、とくに聖書の写本、あるいは法典という意味に使われるようです)
このとき、写される文字は、文字そのものが写されているのでは実はなく、文字列、さらにいえばテキストが運搬する「意味」を実は写している……ということになる。
ですから、変換規則さえ決めておけば、元のテキストの文字列とはまったく違う文字列で「写本」しても構わない。いわゆる「暗号化」というやつですね。
ところが、「画像を写す」あるいは「画像として写す」場合には、これは全く違う……というふうに論をもっていきたいわけですが、チョットマテヨ……と。
テキストを写す場合においても、私の場合ですと、いかなる書体で写すのか、テキストと全く同じ書体にするのか、それとも……ということは、いつも大きな問題になります。
おそらく、印刷術の発明前に、手書きで写本を行っていた人々も、同じように感じたのではないでしょうか。
このように、テキストの段階でさえ、「現象的に現われる形態」と「それによって運ばれる意味」の2重性は大きな意味を持ってきます。
私の場合、文字を写していても、画像を写していても、やっぱりそのことが、いつも自分の中で、どこまでもつきまとって離れません。
でも、実際に写しているときには、さらに別な衝動が働いているようだ……
それは、「写す」ということの持っている、基本的な「ヨロコビ」のようなものかもしれません。
昨日(元旦)、テレビを見ていると、面白い番組をやっていた。
人間が、「私が、私である」という意識、これがどうしてできるのか……ということを取り上げた番組でしたが、その中で「ミラーニューロン」でしたか、人間の脳の中には、他人行為を見て、それを真似るときに興奮するニューロンがある……ということをいっていた。
これは、人間が、人間の社会の中で、人間になっていく……ということの基本になるものだ……というような内容でしたが、私は、なるほどと思いました。
とにかく、写しているときは、面白いのです。
それは、無償の喜び……といいましょうか、とにかく、その行為そのものが面白い。
お寺では、修行の方法として、「写経」というものがあるそうですが、これも、根底には、そのような「喜び」があるのかもしれない。
私は、学生時代に、毎日学校の図書館に通って、『荘子』を内篇の1文字目から写していく……という作業をやってみたことがあります。
今考えると、なぜそのようなことをやったのかワカラナイ。時間の無駄。暇潰し。文庫本で数百円で買える時代に、なぜ手写本など……。
でも、やっぱりそのときは、「写す」ということ自体に快感を感じていたのだと思います。
「写す」ということでもう一つ思い出すのは、漢字を写すときに、わざわざ「袋文字」にして写すと、これにはモノスゴイ?快感がある……ということです。
これは、なぜだか理由はわかりません。
たとえば、チラシ広告などで、太い明朝体やゴシック体で大きく印字された見出し文字。
これを、袋文字に直しながら写します。するとモノスゴイ?快感……脳内はドーパミンの嵐?です。
無心にこれをやっていると、時がたつのも忘れて……といいたいところですが、一方には醒めた意識もあって、「そういう馬鹿なことに耽るな!時間の無駄!非建設的!」と連呼している……そういうかすかな「うしろめたさ」も伴う行為です。
私だけが異常?なのかな……と思っていたら、うちの子が、たしか小学校低学年のときに、全く同じことを目の前でやっているのを見て、愕然とした憶えがあります。
このこと、つまり「漢字を写すときに袋文字にして写すと異常な?快感がある」ということについて研究している人はいないのでしょうか?
2.文字と画像とナマコの味
パソコンでいろいろやりますが、「文字」を打つ場合と、「画像」を扱う場合とでは、明らかに「重さ」が違う。つまり、ファイルの重さのことですが……。
文字は、2進法のコーディングが決まっていれば、比較的軽い情報で扱えるが、画像はそうはいきません。
その意味からすると、人にとって、文字は、相当に進んだ?段階にあるものといえるのではないでしょうか。
つまり、約束事によって成り立っている部分が画像よりも多い。人の脳という情報処理装置に委ねる部分が多い分だけ、パソコン内の情報量は軽くてすむわけでしょう。
そういう意味からすれば、文字の中には、すでに、時間と空間に限定された「文化的背景」というものがぎっしりとある。
昔、学校で、古典ギリシア語の初歩を学んだときの経験です。はじめは、あの不思議な文字の形……それは、まったく判らなかった。ただ、まるまると肥えた字の列が面白くて、しかも綺麗だ……と思った。
私の学んだ教科書は、岩波全書版の、確か松平千秋さんという先生のものでした。このときの岩波全書版のギリシア語のフォントが、まるまると肥えていたのです。
後に、古本屋で、同じ本の以前の版を手に入れましたが、その版のフォントは痩せていて、しかもナナメ(イタリック)だった。もし教科書がこれだったら、私は多分古典ギリシア語をとる気にはならなかっただろうと思った。
とにかく、そんなわけで、まるまると肥えたギリシア文字フォントにとりついて少しずつ囓りだしてみますと、はじめは全く謎だった文字が、すこしずつ……朝霧が晴れて向かいの山が見えてくるように、少しずつ見えてきました。
このとき、人が文字を知っていく……というのはこういうことか!と思った。
だから、翌年、ラテン語の初歩をやることになったときには、困りました。ラテンアルファベットは、もうすでに見慣れたものだったので、ギリシア文字フォントのような魅力がない……どうしよう……。
だけど、見慣れたラテンアルファベットだけれども、古典ローマ期に、石に刻んでいたフォント……やや、これは少しちがうぞ……ということがわかってきた。
今でいうフォント書体としては、オールドローマンということになるのでしょうが、今のオールドローマン系の書体は、やはりルネサンス期以降(?)に、印刷用として、石に刻んだ古典ローマ期の書体を参考にして新しくつくられたものですので、やっぱりホンモノ(?)の古代ローマの書体とは違う。
それは、微妙に違うということじゃなくて、文字自体の持っているDNAみたいなものが、根本的に異なるのです。
それを、「文化的背景」といってしまえばいえるかもしれませんが、やはり、それだけではないものが、私にはどうしても感じられます。文字のもつモナド性といいますか……やはり、文字というものは、非常にインディヴィデュアルな面と、コモン、普遍的な面とを合わせもつ、一種人格的なものさえ備えたものと思います。
秦の始皇帝という人は、かなりグレードの高いワンマンだったみたいですが、文字についてもやっぱりものすごいワンマンぶりを発揮しています。
当時の中国においては、同一の文字に、殆ど無限といっていいくらいの異種書体があった。それは、民族とか共同体とか……どのレベルで差があったのかしらないけれど、もう夥しい数の書体があって、お互いに意志疎通にも障害になっていたとか……。
秦の始皇帝は、それを、強権で一種類のフォントに統一してしまった。結局それが、今「小篆」と呼ばれている書体だとか……。
それも、今の国語協議会ですか?「この書体を使いましょう」というような穏やかなものじゃなくて、違う書体を使ったヤツは死刑!……というほど恐ろしいものだったそうです。
おかげで、秦の国内での意志疎通は極めて向上。しかし、その時点で、豊かな文字群の殆どは消滅してしまった。
きくところによると、ヒトラーもおんなじようなことをやっているみたいですね。
当時のドイツでは、フラクトゥーアと呼ばれる、今、クリスマスデコレーションなんかに使っているのと似た、ちょっと普通では読めないような書体が、印刷物用としてごく一般的に使われていた。
ヒトラーは、こんな複雑怪奇な書体を使っていたんではアカン!……と思ったんでしょう。始皇帝みたいに、強権を発動して、印刷物の書体を全部今普通に使っているような書体(ラテン書体)に変えてしまった。
おかげで、ドイツ国民の識字率は確かに向上したんでしょう。しかし、優雅なかつての印刷用書体は忘れ去られて、そんな文字で印刷された本は、今ではごく限られた人しか読めなくなってしまいました。
文字は不思議ですね。たしかに、2進法コードに変換すれば情報量はきわめて軽くなるけれども、それは、結局、秦の始皇帝やヒトラーと変わらないかもしれません。
文字と絵の違いというものは、実は、きわめてあいまいで、夜の霧の中を漂っているようなものかもしれません。
この問題については、いろんな人がいろんなことをいうけれども、結局どこまでもよくわからない……というのがほんとうのところではないか……という気がします。
わたしも、自分の作品で、画像になったりテキストになったりしまして、その都度、いろいろ考えるのですが、結局いまだに自分なりの結論さえでていません。
その中でやるのは、確かにあまり気持ちはよくないことなのですが……食べたことのないナマコの味のように、私にとっても、見る人にとっても、なにか解決のつかないもやもやの中に消えたり現れたり……で行くもののように思うのです。
3.村上華岳のこと
私の知るかぎり、「画像」というものの不思議さといいますか、「絵」というものの持っている、「絵」というものにしか持ちえない力を最も濃厚に感じさせる「絵描き」は、村上華岳だと思います。
彼の作品を見ていると、いつも「幽明界の境」という言葉が浮かんできます。
彼が描いた、ごく平凡な山道の風景。しかし、その道は私の心を案内して、静かで不思議な、明るいのか暗いのかもわからない、だけどやっぱり歩んでいかねばならない「世界」へと誘いこんでゆくような……。
ドイツの小説家のトマス・マンの作品に、有名な『ベニスに死す』というのがあります。
この作品の中には、主人公のグスタフ・アシェンバッハさんを「黄泉」にさそう案内役ともなる人物が、何度も何度も、繰り返し出てくる。ミュンヘンの街で会った不思議な男、ベニスに向かう船で出会う厚化粧の老人、そして、彼をリド(終焉の地となるホテルのある島)へ運ぶゴンドラの漕ぎ手……。
こういった人物に出会うたびに、アシェンバッハさんは、「世界が異常なものに変貌していく」という奇妙な思いに把われるのですが……村上華岳の絵を見ていると、私は、マンよりはるかにうまく、さらにさらに本質的に、彼は「絵」の中で、そのことをやっているような気がしてくるのです。
マンの作品においては、やはり小説技巧といいますか、上記の人物たちは、実際にマンが出会った人が多いようですが、それでもやはり小説を組み立てていく上でのテクニックを感じます。しかし、華岳の絵にはそれがない……。
と申しますか、画像においては、そのような存在を画像として登場させて、しかもなお、イラストレーションに堕ちない……そのことは不可能ではないかとさえ思います。
イラストレーションに堕ちない……言い方は、ちょっとアブナイ表現で、昨今おしかりを受ける可能性もありますが……でも、実際に画像としてそのような「導き手」を出してしまうと、その限定はキツイものになる……「絵」は、それ自身としての自立性をたちまち失って、「物語を運搬する手段」の位置におとしめられてしまう。
哲学者のカントさんは、『自分以外の人間を、常に、手段としてでなく目的として見るように』ということをおっしゃったそうですが、「絵」にもそのことは当てはまるのであって、「絵」を、なにか別のもの、「理念」でも「物語」でもいいですが、そういう無形のものを有形化、視覚化する手段として用いた瞬間、それは「絵」ではなく「イラストレーション」(説明のための絵)になってしまう。
美術史においては、「イコノロジー」という研究分野があって、いわゆる「絵を読む」ということですか、もともとは、ルネサンス期以前の「絵」を読み解く方法として発達してきた研究分野であると思うのですが、最近では、近代・現代の作品にまで適用されて、「絵を読み解く」ということが、一種のブームになってきているような感さえあります。
しかし、私は、本来の「絵」というものは、読み解かれてしまうものであってはならないように思うのです。
華岳の作品は、ちょっとイコノロジーの手法では、いくらがんばっても歯がたたない。ものすごく静かに、しかし強く、「解釈」を拒み続けます。(またそこが、評論する人にとってはタマラナイ魅力なのかもしれませんが)
幽明界の境……と書きましたが、言葉、文章でそういうものを表現することは当然可能です。言葉や文章を導き手として……という意味ですが。
しかし、「画像」として表現される「絵」でそれを表すというのは……これはものすごいことのように思います。
私が感ずる華岳の世界に共通する体験として……私が以前よく見た夢。
夢で、階段を降り続けています。
暗いのか、明るいのか……水色の、光源がない不思議な淡い光に満たされた、無限に静かで、どこまでもどこまでも続く階段……それを、どこまでもどこまでも降り続けていく……。
降り続けていくうちに、私の身体は実体を失って、魂だけのようになって……それでも、どこまでもどこまでも無限に降り続けていく……。
私は、村上華岳の絵に、このような世界の入り口を感じます。
山肌を描く線の一本一本……その一筆さえもがそのような力を持っている……こんな絵描きは、ちょっとほかにはしりません。
私にとっては、コピーするのが不可能で、コピーする気にさえならない、神社の奥の院のような絵描きさんです。
4.エロスと否視・1
このタイトルだと、どうしても、有名な『ディアーヌの水浴』のことを思い浮かべてしまいます。女神ディアーヌの湯浴みする裸身を見た狩人の青年アクタイオンが、鹿に変身させられてしまうという、あの物語です。
見ることを許されぬものを見たものは、それを語る口を失う……ということが骨格となっているようですが、ここからは、確かに示唆に富むさまざまな文章を導出できるのかもしれません。
これで思い出すのは、これも有名な、マルセル・デュシャンの最後の作品『照明用ガスと、落ちる水が与えられたとせよ』ですね。
フィラデルフィア美術館に安置?されているという、例の『遺作』ですが……頑丈な板張りのドアの、覗き孔の向こうに拡がるジオラマ的光景を、自分の死語25年間は撮影禁止と遺い残した。
ところが、その禁はあっというまに破られて、その内部景観はすでに世界中に出回り、業界ではもう知らぬ人は誰もいない……という状態。一体どなたが最初に禁を犯してディアーヌの裸身を撮影したのか……。
当然、デュシャンは、自分の遺言が守られるとは思っていなかったでしょう。今日の状態はすべて想定ずみとして、「禁を犯す」という人の心さえ作品化してしまったように思える……。
私は、ここで、人が、「作品を見る」ということが、本当はどういうことなのかを、どうしても考えてしまいます。
たとえば、ギャラリーを借りて個展をやります。すると、お客さんが見にきてくれます。お客さんがゼロということは、まずありえません。
作者は、本来居場所のない個展会場にぼー……と立っています。
ときどき、ギャラリーのドアが開いてお客さんが入ってきます。くるくるっと眺めて、去っていく……その間は、大体1分くらいでしょうか。
以前、銀座のギャラリーで個展をやったときは驚きました。一人大体10秒くらい……。銀座は、人は入るけれども、みなたくさんのギャラリーを回らなければならないのでせっかちです。
作者としては当然がっくり……。自分が何年も何ヶ月も苦心してつくった作品が、たったの10秒でわかるのかよ……といいたいけれど、それはいわずに、ドアを開けて去ってゆく客の後姿におじぎをする……。
作品を見る……ということは、一体どういうことでしょうか。
一体、何を見たら、「作品を見た」ということになるのだろうか……?
自分が、だれかの作品を見るときのことを考えてみると、このことの意味はよく判る。
私自身が、だれか別の人の個展会場にいってその人の作品を見るとしますと……とにかく、まず見るわけです。
それで、大体わかったと思えば、その作品の前を離れて次の作品に移る……このくりかえしです。
そのとき、私は、なにをもって「わかった」と思い、なにをもってその作品の前を離れるのか……。
哲学のジャンルだと思いますが、有名な「ブレダンの驢馬」というお話しがあります。
驢馬が一匹います。人間が、その驢馬からまったく等距離の2個所に、まったく同量の餌を置く。
等距離で同量だから、驢馬はそのどちらの餌を選択してもいいわけです。だけど、驢馬からみると、2つの餌はまったく等価となるので、選択を決定する要因がない。
それで、かわいそうな驢馬は、とうとう餓死しました……というお話しなのですが……
もし、ある作品の前に立って、その作品を「見る」までその前を離れない……としますと……「見る」ということを、ただ「網膜に映る」ということで良しとするなら、作品が網膜に映った瞬間にその作品の前を離れて次の作品に映ることができる。
そうすれば、理論的には、ギャラリー滞在時間は、その人の移動速度によることになりますから、短距離選手であれば10秒もかからないでしょう。
あるいは、スケボーでも履いていれば、2,3秒ですむ。
入り口から全壁面が見渡せる「死角なきギャラリー」であれば、それこそナノ秒単位の一瞥で終了します。
しかし、一旦「見るというのはどういうことか」ということにこだわりだすと、事情は一変します。
一枚の作品の前で、ブレダンの驢馬のように動けなくなって餓死した……という人の話は聞きませんので、みな、適当なところで「了解」して、次の作品に移るのでしょうが……。
「フランダースの犬」の主人公みたいに、ルーベンスの絵の前で死んでしまう人もいますが、たいていはなんらかの決定要因があって、作品の前をふわりと離れる。
これは、作者にとってもそうです。自分の絵の前で凍りついて餓死した……という人はいません。
結局、みな、なんらかの時点で「見た」と思ってその前を離れるわけです。
しかし、どこまで究極に見たのか……、なにをもって「見た」としたのか……。
5.エロスと否視・2
ここで、最初の「ディアーヌの水浴」の話に戻りますと……狩人アクタイオンは、確かにディアーヌの裸身を見たのだけれど、それは、どこまで見たのか。
人が衣服を身につけていると、その人を見る人の視線は衣服で止まる。シースルーの場合は別として、衣服の下は不可視です。
ここで、「否視」が成立している。少なくとも、もっと見たい……という人には、衣服が否視の壁になっています。
では、人が衣服を少しずつ脱いでいったら……。
段階ごとに否視の壁が剥がされて、「見える」、「見た」という、その思いを味わうことができる。いわゆる「ストリッピング」ですね。
しかし、ついに、すべての衣装が脱がされて、これ以上脱ぐものがなにもない……という状態になったとき……人の視線は「皮膚」でとまります。
「皮膚を脱ぐ」ということは、普通はやりませんから、「皮膚」は人の、最後の否視の壁です。
だれか有名な人が、たとえば講演会をやる……というとき、行ってみたいな……という気持ちがわいたとしたら、なぜ行ってみたいと思うのか、その理由をいろいろ考えてみます。
講演会の内容が、たとえば後で本なんかに載るとしたら、それを読めばいい。
あるいは、ビデオが発売されるとしたら、姿も声もそれでわかる。
とすると、私の場合、残る衝動は、やっぱり「皮膚を見たい」ということでしょうか。
きわめてミーハー的に、なんとかさんの「皮膚を見たい」。
講演会なんかだと、たいがいの場合、見える皮膚は顔と手だけなのですが……それでも、皮膚を見ると、「見た」という感じを味わうことができる。
講演会に出かけて、「実物」を見るということは、私の場合、どうもそのこと、つまり「皮膚を見る」ということにあるようです。
では、「作品」の場合はどうだろうか。
作品は、たいがいの場合、全部がそこにあります。つまり、隠されていなくて、全部が見えるようになってそこにある。
私は、これがいかんのじゃないか……と思います。
たとえば、作品がなにかに覆われていて、見る人が一枚一枚、その「衣服」を脱がせていくと、少しずつ作品が見えてくる。
ついに最後の一枚を脱がせて作品の「全貌」が現れたとき……人は、アクタイオンのように、その作品を「見た」と思うことができる。
普通は、作品は、常に全裸でギャラリーに架かっているので、人は「前段階の儀式」を通過せずにいきなり全てを脱がされてしまった作品に対面する。これは、一種の「暴力」かもしれません。
ですから、ギャラリーで作品を見るとき……作品の側に「前段階の儀式」を提供するサービスがない分、見る人は、自分の中に、この「前段階の儀式」を構築する必要が生じます。
その意味では、デュシャンの『遺作』はずいぶん親切ですね。人は、まず、木製の頑丈な扉を見て、それからそこにあいた覗き孔を見て、そしてやっとその内部景観に到達する。
それで、人は、「見た」と思いこむことができるわけです。
「25年間撮影禁止」という彼の遺言は、できるだけ多くの人に、「前段階の儀式」を提供しようという彼のむなしい(しかし破られることが予測ずみの)サービス精神だったのかもしれませんね。
だけど、やっぱり、「本当の謎」は、ここから始まる。
全部が脱がされて、全裸の身体がそこにあるとき、人は、それ以上、どうするか。
ここで、問題は、「延長」の世界から「思惟」の世界に移らざるをえない。
スピノザは、「思惟」の世界と「延長」の世界を厳密に平行させて考えたが、にもかかわらず両者は同一であるとした。
私たちは、「延長」の世界をずっとたどってきて、それは無限に深い奥行きであるゆえに、やはりどこかで「途方にくれてたちどまってしまう」わけです。
すると、そこに、「思惟」の世界に通ずる扉がある。
といいますか、「延長」の世界をずっとたどってきたと思っていたけれど、実は、平行して、「思惟」の世界もずっとたどってきていた……ということに気づきます。
ブレダンの驢馬には「延長」の世界しかないわけですが、現実にはそういう存在はありえず、すべて、「延長」の世界と「思惟」の世界が平行している。
「見る」ということのすべての謎は、この「思惟」の世界と「延長」の世界をつなぐ扉にある。
そして、その扉を開く力を「エロス」と呼ぶこともできるのだと……そう思います。
6.導き手としてのエロス
ここで、少々長いですが、マンの『ベニスに死す』からの引用を。
『なぜかというと、美は、プァイドロスよ、よくお聞きよ、美だけが神的にして同時に目に見えるものなのだ。だからして、美は感覚的な者の道なのだ、小さなプァイドロスよ、芸術家が精神に達するための道なのだ。
ところで、ねえ、おまえは信ずるかね、精神的なものに達するために感覚を通る道を歩まねばならぬような者が、いつか英知と真の男性的品格を獲得することができる、と? それともおまえはむしろ(決定はおまえにまかせるよ)、その道は危険にも好もしい道であって、必然的にあやまりに導く、迷いと罪の道にちがいない、と信ずるかね?
なぜかというと、おまえも知っているにちがいないが、われわれ詩人は、エロスが加わって案内者をつとめるのでなくては、美の道を行くことができないのだ。そうだ、われわれがたとえ、われわれの流儀で英雄で規律正しい軍人であろうとも、われわれは女のようなものなのだ。なぜかというと、情熱がわれわれの高揚であり、われわれのあこがれはいつまでも愛にとどまらざるをえないからなのだ、------これがわれわれの喜びで、また恥辱なのだ。」(浅井真男訳、角川文庫版)
これは、美少年タジオの後を追ってベニスの街をうろつき回る主人公の小説家、グスタフ・アシェンバッハの脳裏に浮かぶ妄想の対話で、ソクラテス(=アシェンバッハ)が美少年パイドロスに語りかける形式をとっています。しかし、私の調べたところでは、プラトンの『パイドロス』にはこのような対話は収録されていませんので、ソクラテスの口を借りたマン自身の考えといっていいでしょう。
もう少し引用を続けてみます。
「いまはおまえにもわかったろうか、われわれ詩人は賢明にもなれないし、品格を得ることもできないことが? われわれが必然的にあやまりにふみこみ、必然的にいつまでも不品行に、感情の冒険者たるにとどまることが?
われわれの文体の大家然たる態度はうそで道化だし、われわれの名声と栄位は茶番だし、われわれに対する大衆の信頼はきわめて笑うべきものだし、芸術による民衆と青年の教育は乱暴な、禁止すべきくわだてなのだ。なぜかというと、深淵へと向かう改善しがたい天性的傾向を持って生まれた者に、どうして教育者の資格があろう? われわれは深淵を否認して品格を得たいにはちがいないのだが、どちらに身をかわしても深淵に引きつけられるのだ。」
主人公グスタフ・アシェンバッハは、その作品が教科書にものるほど「大家」としての名声を確立した、いわゆる「押しも押されもせぬ」作家なのですが、その彼が、避暑地ベニスに滞在中に、ポーランド貴族の一家の少年タジオの「美」に惹かれて少年を追い回し、結局自己崩壊に至る物語で、最後のこの妄想が、いわば全編の論理的骨格をなすといえるでしょう。
この妄想は、次のようにしめくくられます。
「たとえば、われわれは、解消させる認識と絶縁する。なぜかというと認識は、プァイドロスよ、品格と厳格さを持たないからだ。認識は知り、解消し、ゆるすもので、定見と形式を持たず、深淵への同情を持ち、それ自体深淵なのだからだ。
さて、この認識をわれわれが決然と拒否するとしよう。そののちにわれわれの努力をひたすら美に、つまり単純と偉大と新しい厳格さ、第二の天真爛漫と形式に向けるとしよう。しかし、形式と天真爛漫は、プァイドロスよ、陶酔と欲念に導き、おそらくは高貴な人間を、彼自身の美しい厳格さが恥ずべきものとして非難するような怖るべき感情の悪業に導き、深淵に------やはり深淵に導くのだ。
われわれ詩人はそこに導かれるのだ。なぜかというと、われわれは飛ぶことはできずに、ただ逸脱することができるだけなのだから。
さあ、もうわたしは立ち去ろう。プァイドロスよ、おまえはここにとどまっているがいい。そして、わたしの姿がみえなくなってから、おまえも立ち去るがいい。」
マルセル・デュシャンに、「ラリー街21番地のドア」というタイトルでしたか、1枚のドアが2つの部屋の共通のドアになっていて、一方の部屋を閉じるともう一方は開く、どちらか一方しか閉じることができない……という不思議な作品があります。
「思惟の世界」と「延長の世界」は、このように、常にどちらか一方しか現われることができない。これは、「人間の理性」における一つの限界なのかもしれません。
私においては、やはり「エロス」がこのドアのような役割を果たしていて、本来全く別の(しかしまた本来同一の)世界は、このドアによって開いたり閉じたり……。どちらの部屋も、マンのように「深淵に通ずる」という考え方もできるのですが……。
「エロス」は、私の考えでは、「美」や「愛」という範疇を越えて、もっと、人間の「生きる意志」に直接に関係してくるような重要な役割を果たしている「導き手」ではないかと思います。ニーチェの「力への意志」に近いものなのかもしれませんが……。
「否視」ということに関係づけていうなら、人間の肉体というものは、一つの闇ですね。
人は、自分の中に一つの闇、謎を持って生まれ、そして一生をその闇、謎とともに過ごし……人が死ぬと、その謎は、世界というさらに大きな闇の中に消えていく……。
肉体のみならず、心というもの、精神というものもそうなのかもしれません。だけど、人の心は、なにかのきっかけに「わかった!」という了解、いわば「閃く光」を感ずる瞬間がある。これは、「世界の了解」であるとともに「私自身の了解」です。
われわれの意識というものは、常に薄明の中にあって、自分自身と世界が奇妙に融合したいろいろなイメージの中に漂っている……という図式でいえば、なぜか、そこに一瞬の光が輝いて、「了解」が生まれる瞬間がある。しかし、それはあくまで瞬間であり、すべては再び薄明の世界に漂う……。
とすれば、その光をもたらす力が、私にとっては「エロス」なのかもしれません。
しかし、たぶん、その光をもたらす力そのものは、「エロス」ではないのでしょう。ところが、その力がこの世界に輝いた瞬間に、それは「エロス」と化す。そして、人は、アシェンバッハさんのように、「光の残像」を求めて、どこまでもどこまでも彷徨い歩く……ということになるのかもしれません。
7.人体のこと
作品の中に、「人体」を登場させると締まります。
最近、CGの発達で、人体を電脳空間に描けるようになりましたが……しかし、実際の人間の身体にくらべると、やはりまだまだ……の感は強い。
一人の人間の持つ情報量というものは、やはり膨大なものだと思います。
それは、「人間にとって」という限定は当然着くのでしょうが……西洋絵画の歴史の中で、「裸体」がきわめて大きなモチーフとなってきたということは……「眼が、人の身体を喰べる」……といいますか、眼にとっての食糧としては、やはり「人体」ほどおいしいものはなかった……といってもいいのではないかと感じます。
広告の世界では、「アイキャッチ」、つまり、人の眼を一瞬で捕らえ、惹きつけるものが重要な要素になるそうですが、成人男性と成人女性では、それは明らかに異なっていて、ノーマルな成人男性の場合、最も強力なアイキャッチは女性の裸身の写真だそうです。
では成人女性の場合になにになるかというと、それは「あかちゃん」の写真だとか。
いささかできすぎたお話しにもきこえますが、一端の真実はあるように感じられます。
私自身、作品の中に「裸体」を描くと、なぜか、それだけで締まる。自分でも安易な一手であると思うのですが、具象図像を描いていくと、どうしても……急流が、巨大な滝になっていくように、必然の流れとして、そちらに向かいます。
人の身体の表面は、粒子が細かい。そのように思います。
世界が、ごく微細な粒子でできているとすると……あくまで人間にとっての話なのですが、人の身体の表面というものは、他のものに較べて、異常に粒子が細かい。
人の身体の表面は、粉ふきいものように、無限に細かい粒子をまとわりつけてそこにあります。
人の心が「エロス」に満たされると、その粒子はますます細かく、ますます膨大な量となって人の身体の表面から噴きだし、舞い上がり、一粒一粒が繊細な輝きに包まれて、渦巻きながら空間を漂います。
私の心は、その輝きに包まれて、強く、強く惹きつけられるのだけれども……やはり、それは、マンのいうように、深淵に向かう道なのでしょう。
人間とは何か……というのは、哲学における永遠の課題だそうですが、これは、単に思惟の問題ではすまず、具体的には、「人間の身体とはなにか」という問題にもなってきます……というよりも、今、そこにある裸身……ですね。これがなにか、なんであるのか……という問題です。
吹きあがる微細な光の粒子の前に、われわれの眼と心は眩まされて、その実体を捉えることはとてもできない……そして、手と眼と心は、協働して、「それを写す」という喜びに耽ります。
これは、確かに品位なき道、品格を欠いた道である……とおもうがゆえに、眼と手は様式を見出し、心はさまざまな論理で武装しようとするが……しかし、この戦いは、もう始める前から「負け」が決まっている戦いです。
そして、結局われわれは、われわれの様式がいかに幼く舌たらずのものであり、また心の紡ぐ論理がいかに幼稚で邪念に満ちたものであるか……ということに気づいて愕然とするわけです。
結局、われわれは、なにかかなうべくもない、圧倒的な力に向かって惹きつけられ、それを「挑んでいるのだ」と思いこもうとしている……のかもしれません。
極論になりますが……「抽象」へ向かう衝動は、いわば「裸身への回避」として生まれてくるものではなかったか……そのようにさえ思います。
8.エロスと抽象
ピエト・モンドリアンが裸木の姿を描いたデッサン。それが、幹や枝の形がどんどん変容して「抽象」になっていく過程。
美術史でよく出てくる「抽象の成立」の説明ですが、私は、このモンドリアンの図像を見ると、なぜか条件反射的に、ル・コルビジェのモジュロールの成立にでてくる図式を思い浮かべます。
線で簡略的に描かれた人体が片手を上げている図像。コルビジェは、人体の、一種の新たなカノンから、彼のモジュロールを生み出した。
すると、連想はすぐに構成主義やモダニズムにつながります。
タトリンの螺旋を描く塔。そして社会主義、共産主義の世界観。さらに、その崩壊……。
あるいは、モダニズムとその崩壊……。
これらを、すべて、「微粒子を噴きだす人体」からの逃避という観測点から観てみたらどうなるだろうか……。
ジャクソン・ポロックに代表される(代表?いやいやというご意見もあるかも)抽象表現主義の諸作品は、同じ抽象でも、私にはかなり異なって見えます。これらの諸作品は、「微粒子を噴きだす人体」という観点から見た場合、これを回避していない……。
エロスを避けず、むしろ「過剰なエロス」にできるだけ正直に奉仕した結果の痕跡のようにも見える……。
それだけのエロスを、あの巨大画面に振りまいてつくったがゆえに、いまでもなお、強力な「癒しの力」を静かに静かに放出している……それは、あたかも半減期の異常に長い放射性元素のように……。
その意味で、抽象表現主義の作品群は、直接的に「人体」を描くということは全くしていないけれども、「なるべく脳の高位機能を介さない人体直接出力」というものを表出し、定着しようと試みたがゆえに、あのような巨大画面が必要であり、そして、その結果として、「噴出する微粒子」を見事に留めることができた……と、そのようにいえるのではないでしょうか。
その意味で、私にとって、ちょっと不思議な作家は、やっぱりジェームズ・タレルさんですね。
彼の作品は、一見……というか一体験として、「人間」とは無縁です。
なぜか、「噴出する人体微粒子」をはるかに超える「宇宙論的存在の微粒子」といったものを感じさせられてしまう。
哲学者のカントさんは、彼の『純粋理性批判』において、人間の理性は、宇宙に存在するたくさんの理性の中の一つにすぎない……ということをにおわせる発言を何カ所もしていますが、タレルさんの作品を見ていると(体験していると)、彼は、人間の理性を超えて、「宇宙に存在するたくさんの理性」を相手にしているのではないか……と思わざるを得ないフシがある。
むろん、人間の理性も、その中の一つとして含まれてはくるのですが。
カント以降の近代・現代においては、「人間以外のさまざまな理性」のことは忘れ去られて、「宇宙に存在する唯一の理性である人間」ということが暗黙の枠組みとなってしまいました(人間以外の知的生命体を探るプロジェクトの愚かさの根源は、この枠組みを意識していないところにあるのでしょう)。
だから、最近はやりの環境問題にしても、結局この枠組みを抜け出られない。この枠組みの中で論を進める限り、新たな展開はありえません。
しかし、タレルさんの作品を見ていると、彼は、直感として、「人間以外のさまざまな理性」のことを知っているのかな……という気がするときがある。
カント以前の思考(西洋における思考)の枠組みには、「人間以外のさまざまな理性」を扱う大きな枠があって、人間の理性というものは、あくまでその一部である……という共通の認識があった。
人が、人の身体の魔力から脱するためには、このあたりが、一つの手がかりとなるのではないでしょうか。
9.自己と他者と皮膚
人の身体の皮膚というものは、一種の臓器なんだそうです。
昔読んだある本(ガモフの科学解説本)に、位相幾何学的にいうなら、人間はドーナツである……と書いてありました。
つまり、球体に貫通孔のあいた形。貫通孔は、口から肛門にいたる消化器官です。
すると、身体の外面、すなわち皮膚は、消化器官の内面と通じていて、ともに人間というドーナツの表面を形成している……ということになる。
これも昔読んだのですが、「人間が豚を食べても人間は豚にならない。なぜだろう」ということを論じている奇妙な本がありました。
たしかに、食物は、人間に食われると、結局人間の身体を造ります。
食物の入り口は口である……と思われるが、実はそうではない。口から食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、肛門は、実は人の身体にとっては「外側」であって、本当の入り口は消化器官の表面なのだ……と。
つまり「同化作用」ということですね。
人の消化器官は、その表面に消化液を分泌して取り入れた食物をばらばらにほどき、要素に還元して、本当の入り口である消化器官の表面から体内に摂りいれる……。
人の消化器官の内部空間(つまりドーナツの孔)というものは、植物にとっての土壌にあたるものだと書いている本もありましたが、まさにそのとおりであると思います。
このように、人は、消化器官の表面で、自分でないものを自分に変える同化作用と、同時に自分であったものを自分でないものに変える異化作用の二つを行っています。
つまり、この意味からすれば、人の消化器官の表面は、明らかに「自己」と「他者」の境界です。
とすると、人の身体の皮膚はどうだろう。
自分の身体は皮まで……と言われると、これは一応誰にでも納得できる論理です。
つまり、人の身体の皮膚は、「自己」と「他者」の境界をなしている……ということは自明のように思えます。
しかし、消化器官の表面に較べて、人の身体の皮膚は、いかにも静かです。消化液を分泌して、皮膚から直接食物を吸収してしまう……という怪物のような人はいないわけです。
たとえば、人の身体がぐるりと裏返って消化器官の表面が外側に出てきた状態を考えると……これはもうモンスター映画の世界です(こういう人を、私は「恐怖の外臓人間」と呼んでいます)
しかし……人の皮膚というものは、一見静かに見えるが、実は、消化器官と似たところのある、一種の「臓器」ではないだろうか。
たとえば……専門家でないのでわかりませんが、「皮膚移植」というのはなかなか難しいということをききます。
いわゆる「拒絶反応」というのでしょうか、人の皮膚は、「自分」と「他者」を峻別して、自分でないものを破壊してしまう「免疫能力」をもっている。
アトピーとか、皮膚の炎症ですね。これらは、「自己」と「他者」を峻別する機能が異常に働いた結果のアレルギー症状である……ともいえる。
人の皮膚は、たしかに消化液を分泌して……というような物凄い?同化作用まではやりませんが、空気や水分は吸収するでしょう。
そして、発汗作用なんかは、これはもう、立派な異化作用ですね。
カメレオンとかある種の水生生物には、自分の身体の色を、環境に合わせて変化させてまわりに溶けこんでしまう、いわゆる擬態の得意な生き物がいます。
これらの生物は、その皮膚が、周辺環境を同化する、一種の同化作用をやっているともいえるのではないでしょうか。
そこまでいかなくても、人の皮膚というものも、一種の同化作用と異化作用を行い、自己と他者の境をそこに「創出」している、一種の臓器……と考えることができます。
そして……おそらく、皮膚というこの臓器は、人の心の状態に微妙に反応して、その機能を精妙に変化させていく能力を持っているのです。
前に、人の皮膚からは、繊細な微粒子が放出されて……ということを書きましたが、人の皮膚表面というものは、そのときそのときの人の心の状態をデリケートに反映して、それを他の人に伝達する、通信器官、あるいは表現手段としての役割も果たすものと思います。
人を見る人……人の心と心の状態により、お互いの身体の表面……皮膚の状態は微妙に変化して、微粒子が皮膚表面から放出され、それによって一種のコミニュケーションが成り立つのではないか……とそのように思えます。
以前、ジョージ・アダムスキという人の『テレパシー』という本に、面白いことが書いてありました。
この、ジョージ・アダムスキという人は、宇宙人とコンタクトし、円盤に乗せられた……という、いわゆるコンタクティと呼ばれる人々の一人なのですが……彼にいわせると、
『テレパシーとは、一種の触覚であり、接触感覚である』
ということなのだそうです。
私は、この部分を読んだとき、なるほど……と思いました。
普通、われわれは、テレパシーというと、遠隔通信の超能力だと思います。
つまり、離れたところへ思念を飛ばす……その思念を受けとる、一種の超能力である……という理解。
しかし、アダムスキいわせると、テレパシーというのはコンタクト、つまり接触感覚であり、これはもう、直接的に「触れてくる」という感覚にほかならないのだ……と。
たとえば、私たちは、あいさつのときに握手をしたりします。
日本人では握手はあまりやりませんが……世界には、あいさつのときに、お互いに抱き合ったり……という濃厚な「コンタクト」を行う人達までいる。
これは、「自己」のぎりぎりのライン、つまり、皮膚表面まで相手の侵入を許す……というサインである……ということでしょう。
とすれば、日本人が、握手さえ普通にやらない……ということは、よそよそしいのではじつはなく、日本人の場合には、そういうことをする必要がないくらい、実は「自己」と「他者」が近いのでは……という解釈も成り立ちます。
要するに、かなり「テレパシー」が効いている状態といいますか、接触感覚がすでにあるから、皮膚まで接触させる必要がない。
抱き合ってあいさつをする人達を見ると、われわれは、なんて濃厚な……と思いますが、実は逆で、そのような人々は、日本人に較べるとはるかに「自己」と「他者」が遠いから、皮膚と皮膚を接触させて「自己」と「他者」の融合を図る必要がある……ともいえるのではないかと思います。
私たちは、皮膚という臓器によって、なにを感覚し、どのように自己と世界をコントロールしているのか……。
絵の中に描かれた人体は、けっこう濃厚なものになりえます。
ところが、彫刻作品として造られた人体は、どうしても一種のオブジェ、生命なき物体と化してしまう。これは不思議です。
むろん、彫刻作品でも、色を塗ったり、表面処理で生々しさを出すことは可能です。しかし、それをやってしまうと、ナントカ秘宝館の人形のようになって、愕然と品位は落ちます。
絵画作品においては、品位を保ちながら、しかも濃厚な裸体……というものが成立し得る。これは、過去の「巨匠」の幾多の作品が証明しているところです。
しかし、彫刻作品においては、「巨匠」の作品は、品位は充分なれど濃厚さは雲散霧消……少なくとも、臓器としての皮膚が発する濃厚なテレパシー、噴出する微粒子のようなものは感じられません。
映画なんかで、死人の役。あれはなかなか難しい……と思います。
人形を使ったりすると、死んでいるんだから問題ないはずなのに、なぜかわかってしまう。
人は、死にたては、まだ皮膚は生きていて、濃厚に「テレパシー」を発散しているんじゃないでしょうか。
だから、死人の役でも結局俳優を使う。
生命というものは不思議で、生きているということは、結局皮膚の細かい細胞の一つ一つが生きている……生きて、そこから濃厚な微粒子を噴出している……。
人の皮膚は、言葉にならない言葉で、人の直接の生の意識、生きているということの意味、そして生きる意志を噴出している。
なぜ、平面絵画だけがそれをうまく捉えられるのかはわかりませんが、「裸体を入れると画面が締まる」ということの理由の一つはそこにあるのではないかとも思います。
10.不気味の谷
以前読んだ本に、「不気味の谷」というお話しが載っていました。
別に怪談の本ではなく、杉浦康平さんというデザイナーの書いた文章の中にですが……。
「不気味の谷」というのは、杉浦さんの話では、確かロボット工学かなにかの先生が使った用語だそうで、「人」と「人ならざるもの」のぎりぎりの境界に現われる深い深い谷……だそうです。
横軸に「人間らしさ」を、縦軸に「親近感」をとります。(もう少しちがう言葉だったかもしれませんが)
つぎに、「人形」とか「人体彫刻」とか「マネキン」とか「ロボット」なんかを横軸にプロットしていきます。当然「人間」も入ります。
「人体彫刻」より「人形」の方が「人間」に近い位置にくる。「マネキン」はもっと人間に近いかもしれない。
「ロボット」は、形や動きによってさまざまですが、最近おなじみの「アシモ」君などは、動いている様子は「マネキン」より「人間」の近くに位置するかもしれません。
横軸の位置が「人間」に近づくにしたがって、縦軸の「親近感」もどんどん上昇していきます。
それで、富士山のようなきれいな曲線を描いて、頂上で「人間」に……と思うと、どうもそうではない。
むろん、頂上は人間になるのですが、「人間」に至る寸前で、それまできわめてスムーズに上昇曲線を描いてきた「親近感」が、突然ドーンと落ちこむ深い深い谷がある……。
その、もっとも極端な例として、「人間」のすぐ脇に「動く死人」と書いてありました。
なるほど、これは不気味だ……。
ということで、「不気味の谷」というそうです。
私が、ずっと子供のころに読んだ本に、とても興味深い話が載っていました。
ある超能力者のお話し。
その人は、人形に死人の魂を宿らせる……という、一種のイタコのような能力の持ち主だそうです。
それで、たとえば息子が南方で戦死した……という夫婦がやってくる。
夫婦は、彼に、息子の死んだときの様子を知りたい……と頼むわけです。
すると、超能力者は、なにやらモゴモゴ……だったかどうかは忘れましたが、なにやらやると、傍らの人形が立ち上がる……。そして、銃剣を構えた格好で走り出す……と、突然、ばったり倒れる。
夫婦は、それを見て感涙の嵐……ああ、わが子はこのようにして死んだのか……と。
このお話しを読んだとき、私は、なにか変だな……と思った。
べつに、人形が動くということに疑いを持ったわけではありません。世の中広いから、そんなこともあってもいいような気はします。
私の疑問は、もう少し論理的な部分に関してでした。
生命のない人形に魂を呼んで、動かすことができるとしたら……
その人は、たった今、死んだばかりの人に、その死んだ人の魂を入れて、死体を動かすこともできる筈です。
としたら……その死人は、生きている状態と一体どこが違うのだろうか。
魂にとっては、身体は自分の身体だし、当然魂も自分の魂だ……自分の魂が自分の身体に入って身体を動かすということは、それはもう、生きている状態と区別がつかんのではないだろうか……。
いったい、身体にとって、魂にとって、そして自分にとって、生きているということはどういうことなんだろうか……。
それにしても、死人の魂が死人の身体に入ってそれを動かす……というのは、これはもう究極の不気味の谷にはちがいありません。
たとえば、焼魚。これを、たいがいの人は、「魚の焼死体」とは見ない。
では、鳥の丸焼きはどうだろうか……。これは、人によっては「鳥の焼死体」と見るかもしれない。
豚の丸焼きとなると……これはもう、多くの日本人にとっては「豚の焼死体」以外のなにものでもない……。
「人間の焼死体」は、ほぼ絶対に、「食べ物」にはなりません。
同じものが、「うまそうな食い物」になったり「焼死体」になったりするのはなぜだろうか……。
これは、明らかに「不気味の谷」周辺の出来事のように思いますが……。
たとえば、風邪をひいたとします。
寝込むほどでもないので、仕事にでかける。
職場で、ゲホゲホゲホ……と咳をしたりすると、「大丈夫か」とみな心配してくれる。
しかし、同時に「うつされたら大変」という心も、やはりみな持つわけです。
その意味で……風邪ひきさんは、「人間」から「不気味の谷」に落ちかかる位置にいる。
風邪くらいならまだいいが、インフルエンザだともっと「不気味の谷」に寄る。コレラや天然痘やエイズや……その他諸々だと、さらにさらに「不気味の谷」の方に追いやられてしまいます。
この意味で、「人間」という現象は、その内側に「死」と「生」を合わせ持つが故に、まわりを「不気味の谷」に取り囲まれて中天にかかる孤独な月のようなものかもしれません。
11.豊饒と欠如のエロス
「不気味の谷」の最大の特徴は、「エロスの欠如」ではないかと思います。
そして、それは、「そのもの」に存するパラメータではない。
つまり、「エロス」は、たとえば誰々の体重が何キログラム……というような形で、「そのもの」に存在する属性ではないのです。
「エロス」は、ギリシア神話では、ポロスつまり豊饒を父とし、ペニアすなわち貧窮を母として生まれた……といいます。
ということは、それは、一種の方向性である……なにか、一種のベクトルのようなものですね。マイナスからプラスに向かう流れ……一種の電流であり……エネルギー、力の流れであり……また情報の流れであるのかもしれません。
マルセル・デュシャンの「大ガラス」……これは、ある意味では非常にわかりやすい作品かもしれません。
上下に分断された「花嫁」と「独身者」。そして、その間を瞬間的につなぐ「電気的接触」……
アンドレ・ブルトンの「美とは、痙攣的なものである」……という言葉を思い出します。
能では、シテとワキという二つの役割が必ず登場しますが……この図式が、私には、どうしても「花嫁」と「独身者」に重なって見えてきます。
舞台には、まずワキが登場して長々と口上を述べる。しかし、主役であるシテが登場すると、ワキは舞台のそでの、地謡に近い位置に定着して座り、シテの舞を「見る」役となります。
シテの舞は、普通の舞踊の感覚でしたら、客席にいる観客が見ればそれでいいわけです。
しかし、能においては、観客が見る「前に」、ワキすなわち「見る役」のものが見る。
これは不思議です。こういう不思議な「演劇」というものが、世界にあるのだろうか?
シテの舞は、実は、ワキが「見る」ことによって、ようやく観客に「見える」ものとなる
のです。
12.「否視」−− 夜の闇のエロス
ここで……私の心は、やはり「否視」INVISI(アンヴィジ)というテーマに戻ります。
一枚の絵。
それは、いくら見尽くそうと思っても、「見える」ものではない。
それは、その絵そのものを見ようと思うとき、必ず見えなくなる。
これは、存在そのもの、存在の基底にかかわる、「解けない謎」といいますか、「問いのない答」といいますか……。
私が思うには、人が、絵を見た……と思いこむとき……そこには、なにか必ず別の要因が働いているように思います。
つまりは……絵そのものではなく、なにかに媒介されてそこにある「絵の影」を見て、「絵を見た」と思いこむ……ようなものではないでしょうか。
能において、ワキの存在で、はじめてシテの舞を「見た」となるように……それが「否視」INVISIを軸とした場合の、世界の基本的なからくり……になっているような気がします。
「世界は深い。それは、昼が考えるよりなお深い」……とは、ニーチェの言葉ですが……すべてのものの存在が闇の底に沈む深夜に……「見る」ということが、まったく意味をなさなくなる深い闇の中において、なにかが生まれてくる……しかし、それは、人には見えず、やはり語ることもできません。
京都の上賀茂神社では、「みあれのまつり」という神聖な行事が、古代から連綿と伝えられて今に至っているとききます。
新緑のころ、真夜中に、上賀茂神社の神官数人が、神体山である神山(こうやま)に登ります。
頂上に着いた神官たちは、夜の深い闇の中で、「神の誕生の儀式」を行う。
この儀式は、上賀茂神社のすべての儀式中最も神聖な儀式とされ、神官以外の参加は絶対厳禁とか。だから、いままで、一回も報道されたことはないそうです。
「かみおろし」で誕生した「神」(ワケイカヅチノオオカミ)は、神官に奉載されて山を降り、本殿に鎮座します。
つまり、この儀式までは本殿はカラッポ。お詣りにくる人は、カラッポの神社を拝んでいるということになるのですが……。
この神聖な儀式が終了すると、はじめて神社に「神の魂」が入る。そして、そのときだけ本殿に宿る「ワケイカヅチノオオカミ」を参拝にくる天皇の行列が、今に行事として伝わって、例の有名な「葵祭り」となったということです。
あるいはまた、西洋のお話し。
ヨーロッパの古い教会で、クリスマスイブの夜に、すべての明かりが消され、あたりは真の闇に沈みます。
すると……闇の中に、どこからともなく響いてくる単旋律……、最初の聖歌が聞こえてきます。
暗黒の中に、最初の生命のきざしとして浮かびあがる一つの声……。
この響きを受けて、暗闇に最初の光が輝く。
一本の蝋燭に灯がともされます。
世界は、失った光を再びとりもどした……しかし、それと同時に、深い深い真の闇は失われます。
聖歌は次々と歌い継がれ……それとともに、蝋燭が一本、また一本とともされていきます。世界に光と影が生まれ、形が生まれ、色が生まれて……そして、夜明けの光とともに、すべてが甦ります。
INVISI 否視を導くエロスは、どこにいるのか……。
あるいは、この世界に「エロス」として現われる神秘な力は、いったいどこからやってくるのだろうか……。
カントさんは、彼の哲学の根幹をなす概念として、「物自体」(ディング・アン・ジヒあるいはヌメノン)ということをいっています。
人間は、物自体を認識することはできない。
しかし、私たちは、ヌメノンの世界からの働きかけを常に受けています。
そして……グスタフ・アシェンバッハのように、「エロス」と化したその働きに導かれて「深淵」に向かうのかもしれません。
人を「見ること」に駆りたて、そしてついに否視へと導く代理者、エロスとは、いったいなんだろうか……。
それは、私にとって、永遠に解けない、そして解こうとすること自体が自分にとっては「代理者の殺戮」になるという矛盾をはらんだ問いかけです。